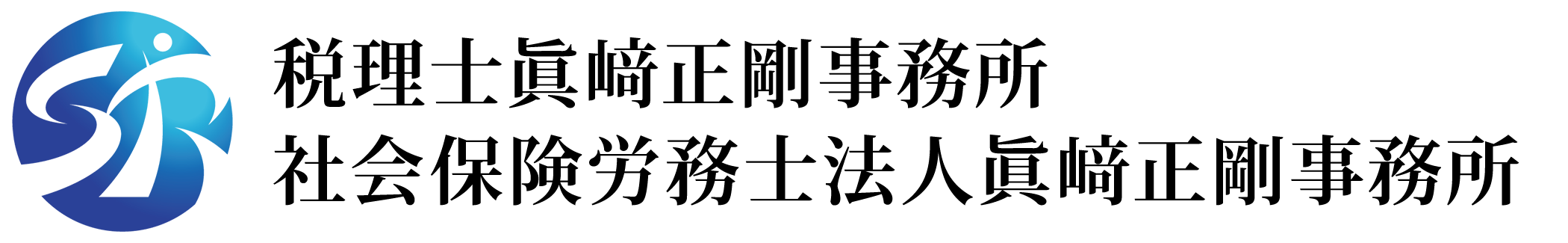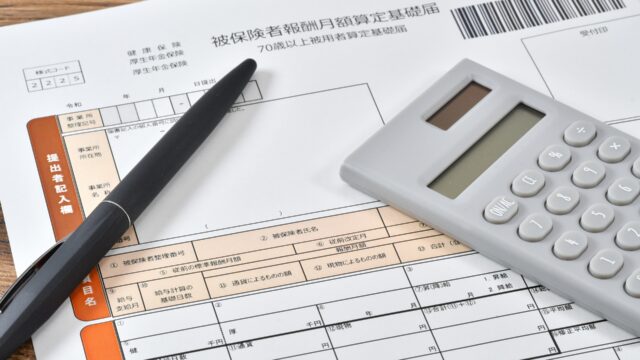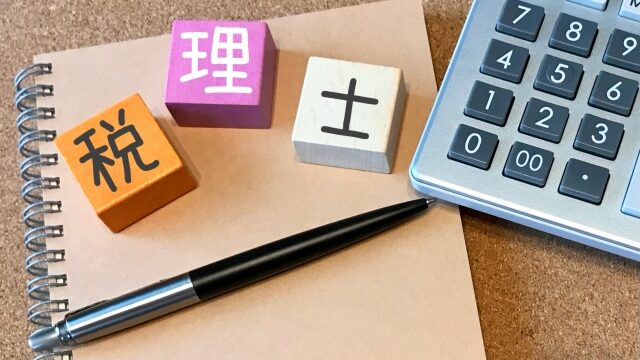前回のコラムでは、労働基準法の基礎的な概念について紹介しました。原則的に、雇用契約というのは「1日8時間・週40時間」とされていますが、業種や業態によっては例外も認められています。
また、労働基準法を遵守しなかった場合、会社に罰則が課せられる事があります。どんな時に法律違反となってどの程度の罰則が課されるのか、今回のコラムでは「特殊制度」「制限のルール」について深堀りしていきます。
勤務時間の例外「変形労働時間制」
労働基準法第32条では、使用者は原則として労働者に対して、休憩時間を除いて1日8時間、週40時間を超えて働かせてはいけないと定められています。ただし、業種や事業場の規模によっては「特例措置対象事業場」という制度があり、法定労働時間の枠を1日8時間・週44時間に緩和できる場合があります。
製造業・商業・小売業・接客業など、繁忙期と閑散期の業務量に大きな差があるような業種では、「変形労働時間制」が取られていることが多いです。変形労働時間制を導入すれば、月単位・年単位で労働時間を調整することも可能になり、特定の週や日では法定の枠を超えて労働をさせても、平均して許容範囲内であれば違法でなくなります。
ただし、就業規則で定める必要があるほか、業務の実態に応じながら休日の設定を調整していかなくてはなりません。厚生労働省が定めた基準を逸脱すると「変形労働時間制」を採用していたとしても罰則の対象になります。
割増賃金・時間外・休日・深夜労働のルール
原則の労働時間を超えた労働や休日労働、深夜労働には「割増賃金」が必要です。これを適切に設計しないと、未払残業代などの労務トラブルにつながります。
時間外労働(法定時間超過)には25%以上の割増率、休日労働(法定休日)には35%以上、深夜(22時〜翌5時)には25%以上の割増が必要です。複数条件が重なった場合は、それぞれの割増が加算されるため、従業員がどの条件で働いたかを明確に記録しなくてはいけません。
また、休日労働を行わせるには、事前に36(サブロク)協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。特別条項付き協定を設ける場合でも、年720時間という法令上の上限があるため、過重労働を防止する管理体制が必要になります。
休日・法定休日と所定休日・休暇制度について
会社側は雇用している従業員に対して、適切な日数分、休日や休暇を付与する必要がありますが、その前に「休日」と「休暇」の違い、そして「法定休日」と「所定休日」の区別を理解しておきましょう。
「休日」とは、労働契約上、労働義務がない日のことを指します。休日には「法定休日」や「所定休日」などがありますが、両者の違いは次の通りです。
・法定休日…労働基準法第35条で定められている、少なくとも週に1回、または例外的に4週に4日の休日
・所定休日…企業が就業規則等で独自に定める休日
法定休日に勤務した場合、休日勤務扱いとなり35%の割増賃金を支払う必要があります。
所定休日の制定には法律上の義務はありませんが、多くの企業が週休二日制を採用しており、法定休日と所定休日をセットのようにして設定していることがほとんどです。法定休日の休日出勤と、所定休日の時間外労働とでは、割増賃金の計算方法が異なるので、就業規則で明確にその違いを定めておく必要があります。
一方、「休暇」とは、本来は労働日にも関わらず、会社がそれを免除した日のことです。年次有給休暇や慶弔休暇、育児・介護休業などがこれにあたり、従業員が自ら会社に申請することで取得できる休日となります。
労働条件の明示・契約変更・制裁禁止と書面化義務
労働基準法第15条では、使用者が労働契約を結ぶ際、賃金や労働時間などの労働条件を文書で明示する義務があります。創業・起業したばかりの雇用契約では、稀に口頭だけでの労働契約が結ばれていることがありますが、労働基準法違反になるほか、賃金未払いなどの労務トラブルのもとになるので、文書は必ず明示しておきましょう。
また、文書に記載されている労働条件の変更を行う場合には、合理的な理由と、労働者への説明・同意が必要です。従業員が変更に了承した場合も、その内容は記録しておく必要があります。
次項で取り上げる「制裁(懲戒処分)」についても、事前に就業規則へ明記し、労働者に周知していない場合は、無効となる可能性があります。
解雇予告・解雇制限・解雇無効について
労働者を解雇する際には、30日前の予告が必要であり、これを行わない場合は30日分の平均賃金を支払う必要があります(労働基準法第20条)。たとえば、20日前に予告を行った場合は、10日分の解雇予告手当の支払いが発生します。
また、解雇を有効に行うためには、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。これらが欠けている場合は、解雇が無効となり、従業員からの損害賠償請求や復職請求に発展することもあります。
さらに、産前産後休業、育児休業、労災療養中の労働者に対しては、原則として解雇が禁止されています。解雇に関するルールは、就業規則に明記し、整理解雇の場合は手続きの合理性を確保することが大切です。
まとめ
今回は、「労働基準法の基礎(補足編)」として、法定労働時間の特例制度、割増賃金ルール、休日と休暇の違い、労働条件の明示義務、そして解雇に関する制限や注意点について解説しました。前回の記事と合わせて読むことで、労務管理の全体像がより明確になってくるでしょう。
特に創業期や中小企業では、これらのルールを理解していないことでトラブルにつながるケースが多く見受けられます。トラブルを未然に防ぐためにも、制度設計・就業規則の整備・労働時間管理などを計画的に行うことが必要です。
「自社に適した就業規則を作りたい」「法令に適合した労働時間管理をしたい」などのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
執筆者紹介

- 税理士眞﨑正剛事務所 社会保険労務士法人眞﨑正剛事務所
- 東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。
慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」
最新の投稿
 会社設立コラム2025年12月25日時短勤務の従業員 給与計算の方法は?
会社設立コラム2025年12月25日時短勤務の従業員 給与計算の方法は? 会社設立コラム2025年12月21日創業直後でも整備しておきたい、ハラスメント対策
会社設立コラム2025年12月21日創業直後でも整備しておきたい、ハラスメント対策 会社設立コラム2025年11月25日税務調査に入られやすい会社の特徴とは?
会社設立コラム2025年11月25日税務調査に入られやすい会社の特徴とは? 会社設立コラム2025年11月21日副業社員を雇う際の労務・税務リスクとは?
会社設立コラム2025年11月21日副業社員を雇う際の労務・税務リスクとは?