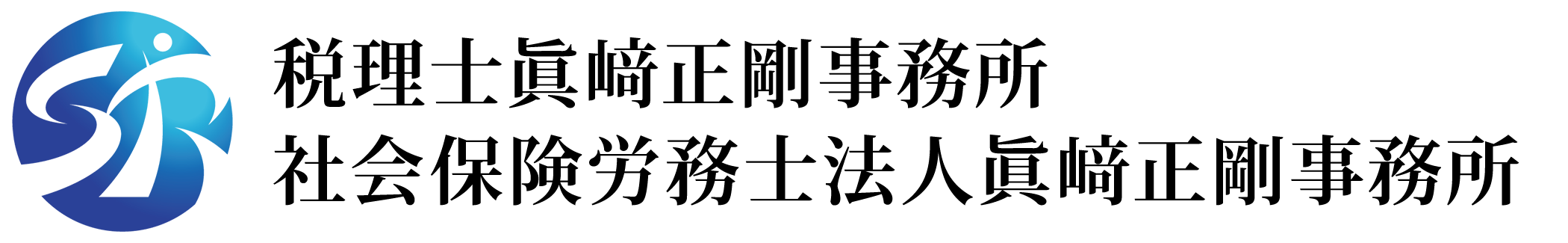会社を設立したばかりの創業者は、どうしても事業の立ち上げや営業活動に注力しがちですが、創業期の経営者として重要な仕事の一つが「労務管理の基盤を築くこと」です。従業員を雇用するとなると、労働法令に基づいた対応が必須で、これを怠ると労使トラブルや行政からの是正指導を受ける可能性があります。
すぐに従業員を雇用する予定がないという人でも、事業拡大が進めば、必ず人を雇うタイミングがやってきます。その時に備えて、創業直後から意識して労務管理の整備を進めるべきでしょう。
そこで今回は、社会保険労務士の視点から、創業初期に知っておくべき労務管理のポイントを解説します。これらの知識を備えておくことで、安心して組織づくりに取り組むことができるようになるでしょう。
1. 雇用契約書と労働条件通知書の整備
従業員を雇用する際に必ず交付すべき書類が「労働条件通知書」です。
労働基準法では、雇用主が賃金や労働時間、休日などの基本的な労働条件を書面で明示することが義務付けられており、雇用契約を結ぶタイミングやその直前に、書面として発行するケースがほとんどです。また、労働条件通知書に記載されている内容のほか、「雇用契約書」を双方が署名・押印する形式で取り交わすことになりますので、これも事前に用意しておきましょう。
特に創業時は、家族や知人を雇うケースも多く、労働条件や報酬なども口約束で済ませてしまうことがあるのですが、これは後々のトラブルにつながるので避けましょう。曖昧な取り決めによって、元々の人間関係が崩れていくケースは、残念ながら非常に多いのです。
例え信頼できる間柄であっても、労働条件や契約内容は明文化し、誰が見ても分かりやすい形で残すことが重要です。
2. 就業規則の作成と届出
常時10人以上の労働者を雇用する場合、「就業規則の作成」と「労働基準監督署への届出」が義務付けられています。就業規則には、始業終業時間、休憩、休日、賃金、退職に関する事項などを定める必要があります。
創業時は従業員が少数であっても、将来的に増員を予定しているのであれば、早い段階から就業規則を整備しておく方が良いでしょう。また、労働者と会社側でのルールを明文化しておくことは、企業を経営する上での指針となるので、業務の安定にもつながります。
なお、就業規則は単なる形式的な文書ではありません。今後育っていくであろう、企業文化の基盤とも言えるものです。会社の今後の方向性を定めるものでもあるので、ビジョンや理念を持っているのであればそれも伝えた上で、社労士と相談しながら、実情に合った内容を構築することが大切です。
3. 労働時間と給与管理のルール化
「創業期」には、経営者も従業員も一人が担う業務が多岐に渡るため、労働時間が曖昧になりがちです。ですが、労働時間の管理は、労務管理の基本中の基本であり、最重要ポイントの一つです。時間外労働や深夜労働を行う場合には、「36協定の締結・届出」が必要であることも忘れてはなりません。
また、賃金台帳や出勤簿の整備、割増賃金の支払いなど、賃金に関する法的ルールにも注意が必要です。労働時間に応じた給与計算ができていないと、後の是正勧告や遡及支払いを受けることになります。実際、創業期に支払われていなかった残業代を、退職する社員が遡って請求するという事例は、本当に多いのです。
こうしたトラブルを避けるためにも、クラウド型勤怠管理システムの導入などで、早期から適切な管理体制を整えることがおすすめです。導入費用も高くなく、人数が増えても継続して利用できるので、経営者自身の労務負担も軽減されます。
4. 社会保険・労働保険の手続き
法人設立と同時に、代表者であっても社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられています。また、従業員を1人でも雇用すれば、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きも必要です。従業員を雇用した場合は、5日以内に手続きをしなくてはいけません。
創業時はこれらの保険手続きが後回しになりがちですが、未加入状態が続くと事業主責任が問われるだけでなく、従業員との信頼関係にも影響します。特に労災事故が発生した場合、保険に未加入だと大きなトラブルとなります。
保険に加入することは、従業員に安心して働いてもらうためでもありますし、会社の社会信用力にも直結するものです。後回しにせずに、必ず対応するようにしましょう。
5. 補助金や助成金の活用に備えて
創業期には資金繰りが厳しい場面も多いので、補助金や助成金を活用したいと考える経営者も多いでしょう。ただし、補助金や助成金の受給には、「労務管理体制が整っていること」が要件とされていることがほとんどです。
例えば、厚労省の「キャリアアップ助成金」や「両立支援助成金」などは、受給要件として次の項目を挙げています。
・就業規則や労働契約書の整備
・正確に労働時間を管理しているか
・法定帳簿の完備 など
労務整備ができていないために、補助金・助成金を申請できなかった…という企業も少なくありません。本質的な意味合いではないかもしれませんが、労務管理を適切に行わなかったら、こうしたデメリットがあるということも、覚えておくといいでしょう。
まとめ
創業時の「労務管理」というのは、単なる事務作業に感じられるかもしれません。しかし、従業員との信頼関係を築き、企業の成長基盤を固めるために非常に大切な取り組みです。
雇用契約・就業規則・勤怠管理・保険手続き、といった基本的な労務管理を、法令に則って適切に行っていくことが、安定した事業運営の基盤になります。
不安な点があれば、早期の段階で社労士など専門家のアドバイスを受けることで、より安心して創業活動に集中できるようになるでしょう。特に専門性が高い、節税対策や資金調達については、適宜アドバイスを受けながら進めていくことで、安定的な経営につながると思います。
執筆者紹介

- 税理士眞﨑正剛事務所 社会保険労務士法人眞﨑正剛事務所
- 東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。
慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」
最新の投稿
 会社設立コラム2026年1月25日外国人雇用で必要な手続きや注意点
会社設立コラム2026年1月25日外国人雇用で必要な手続きや注意点 会社設立コラム2026年1月21日創業時から備える、LGBTQへの配慮 最低限押さえるべきポイント
会社設立コラム2026年1月21日創業時から備える、LGBTQへの配慮 最低限押さえるべきポイント 会社設立コラム2025年12月25日時短勤務の従業員 給与計算の方法は?
会社設立コラム2025年12月25日時短勤務の従業員 給与計算の方法は? 会社設立コラム2025年12月21日創業直後でも整備しておきたい、ハラスメント対策
会社設立コラム2025年12月21日創業直後でも整備しておきたい、ハラスメント対策