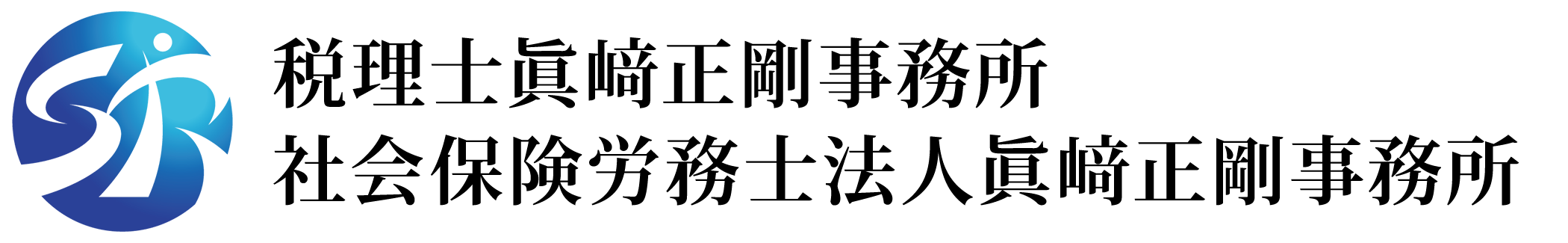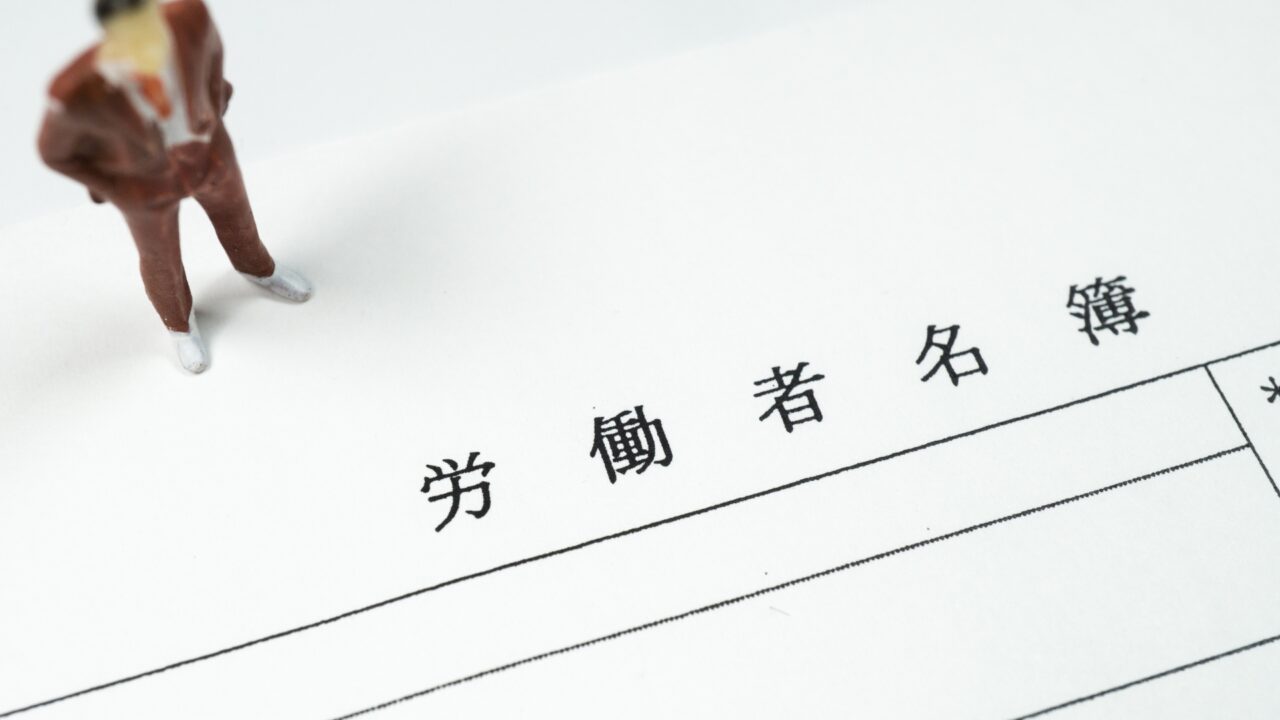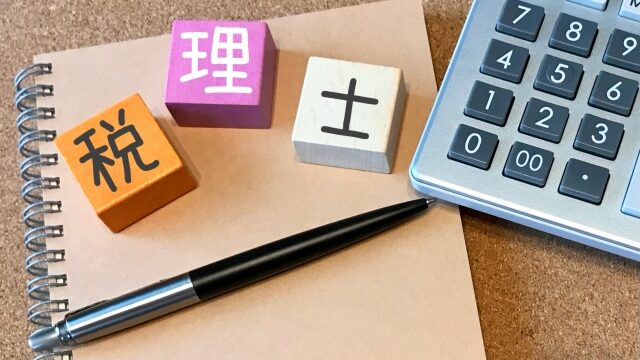2019年から本格的に進められている働き方改革を契機に、労働分野における企業の情報管理が厳しくなってきました。その基本となるのが法定帳簿(労働基準法ほか各種法律で定められた帳簿)の整備ですが、意外とその詳細な整備が抜け落ちて運用されていることもしばしばあります。
そこで今回は、労働基準法に準拠するための帳簿整備として次の4つの帳簿「賃金台帳」「労働者名簿」「出勤簿」「年次有休取得管理簿」について説明していきます。
「法定四帳簿」の種類と、その役割
労働基準法では、労働者の適切な労働環境の把握が必須事項となっています。
そこで重要になってくるのが、事業所または従業員ごとの労働環境を記録した、各種帳簿の整備です。労働契約の基本情報や、労働者自身の個人情報、出勤記録、年次有休暇取得の記録、これらそれぞれの役割を担う4つの帳簿が「法定四帳簿」と呼ばれています。
ところが、特に中小零細企業において、完璧に整備されているとは言い難いのが実態。「帳簿自体は一応作成しているものの、必要記載事項が網羅されていない」、「(2019年に作成が義務化された)年次有給休暇管理簿が未作成」というケースが散見されていますので、今一度、法定四帳簿の概要と必須記載項目について確認しておきましょう。
賃金台帳
賃金計算の基になる基本的な帳簿です。
必要記載事項は、氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数(深夜・休日・残業時間を含む)、基本給及び手当額、賃金控除額などです。
事業所ごとに作成し、賃金支払いの都度、遅滞なく労働者ごとに記入する必要があります。
「賃金台帳を作っていない」という現場は非常に少ないですが、その取扱いについて不備があるケースも多く問題視されています。例えば、労働時間や残業時間、深夜労働時間数などの時間がない、必要な保存期間を満たしていない、といったケースです。
他にも、給与明細と賃金台帳を混同している場合もよく見受けられ、その結果、賃金台帳としての必要記載事項を満たしていないこともあります。
労働者名簿
従業員の存在を確認するための帳簿です。
必須記載項目は、氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務、雇入年月日、退職年月日、死亡の年月日およびその原因です。
事業所ごと、また労働者ごとに作成する必要があり、内容に変更があれば遅滞なく訂正しなくてはいけません。
労働者名簿でよくある不備は、「履歴など」の未記載、そして保存期間を満たしていないという点。特に、「従業員の退職と同時に書類を処分してしまった」というミスも多いのですが、「最新の記載日から3年間」は保存が義務付けられているので注意しましょう。
また、旧工場法時代からある古参の帳簿なので、当時のルールである「本籍地の記載」をそのまま続けている老舗企業もよくありますが、1997年以降は本籍地の記載は削除されているので、こちらも対応する必要があります。
出勤簿
労働時間を記録した帳簿です。
氏名、出勤日、出勤日ごとの始業・就業時間、休憩時間、残業時間を記載します。
法条文には明記されていませんが、厚労省のガイドラインにより「労働関係に関する重要な書類」であると明記されているので、事実上、作成は必須です。
「始業・就業時間が毎日同じで、手書きされている」といった場合、勤務時間の詐称を疑われてしまいかねません。この帳簿においては、客観的事実を記録することが必須ですので、打刻システムなどを使って、正確な時間を記録するようにしましょう。
年次有給休暇管理帳簿
社員の有給休暇取得状況について管理するための帳簿です。
必要記載項目は、年次有給休暇の取得日、付与日、日数で、労働者ごとに作成します。
働き方改革が本格的に推進された2019年(平成31年)4月から、追加で義務化された帳簿です。運用から6年経ってはいますが、そのほかの帳簿と比べると義務化されてから日が浅いので、認知度が低いことが課題とされています。
法定四帳簿の保管期限は3年
これらの4つの帳簿は、3年間保存しておくことが義務付けられています。保存方法は、紙でも電子でも構いませんが、最近は多くの企業が電子で保存しています。なお、保存規定に違反した場合にも、罰則が適用されることがあるので注意しましょう。
まとめ
労働関係の管理における重要な帳簿、「法定四帳簿」について解説しました。創業したばかりで、経営者がバックオフィス業務も兼務しているとなると、特に抜け漏れが多くなってしまうのがこれらの帳簿類です。
不備があると罰則を課せられてしまうので、適切な管理が求められますが、特に2019年に始まった「有給休暇取得管理表」は、その存在自体を知らないという経営者も多いので、知識は必ず身に着けておきましょう。
とはいえ、本業の傍ら労務管理を完璧に行うのは、経営者にとって非常に負担が大きいのも事実。不安がある方はぜひ一度、相模原・町田・座間・海老名会社設立支援センターにご相談下さい。法律に則った適切な帳簿作成をご支援させて頂きます。
執筆者紹介

- 税理士眞﨑正剛事務所 社会保険労務士法人眞﨑正剛事務所
- 東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。
慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」
最新の投稿
 会社設立コラム2026年1月25日外国人雇用で必要な手続きや注意点
会社設立コラム2026年1月25日外国人雇用で必要な手続きや注意点 会社設立コラム2026年1月21日創業時から備える、LGBTQへの配慮 最低限押さえるべきポイント
会社設立コラム2026年1月21日創業時から備える、LGBTQへの配慮 最低限押さえるべきポイント 会社設立コラム2025年12月25日時短勤務の従業員 給与計算の方法は?
会社設立コラム2025年12月25日時短勤務の従業員 給与計算の方法は? 会社設立コラム2025年12月21日創業直後でも整備しておきたい、ハラスメント対策
会社設立コラム2025年12月21日創業直後でも整備しておきたい、ハラスメント対策