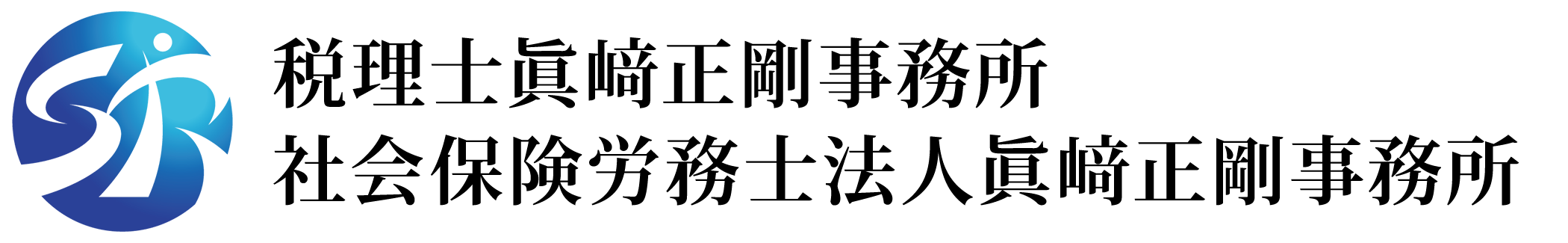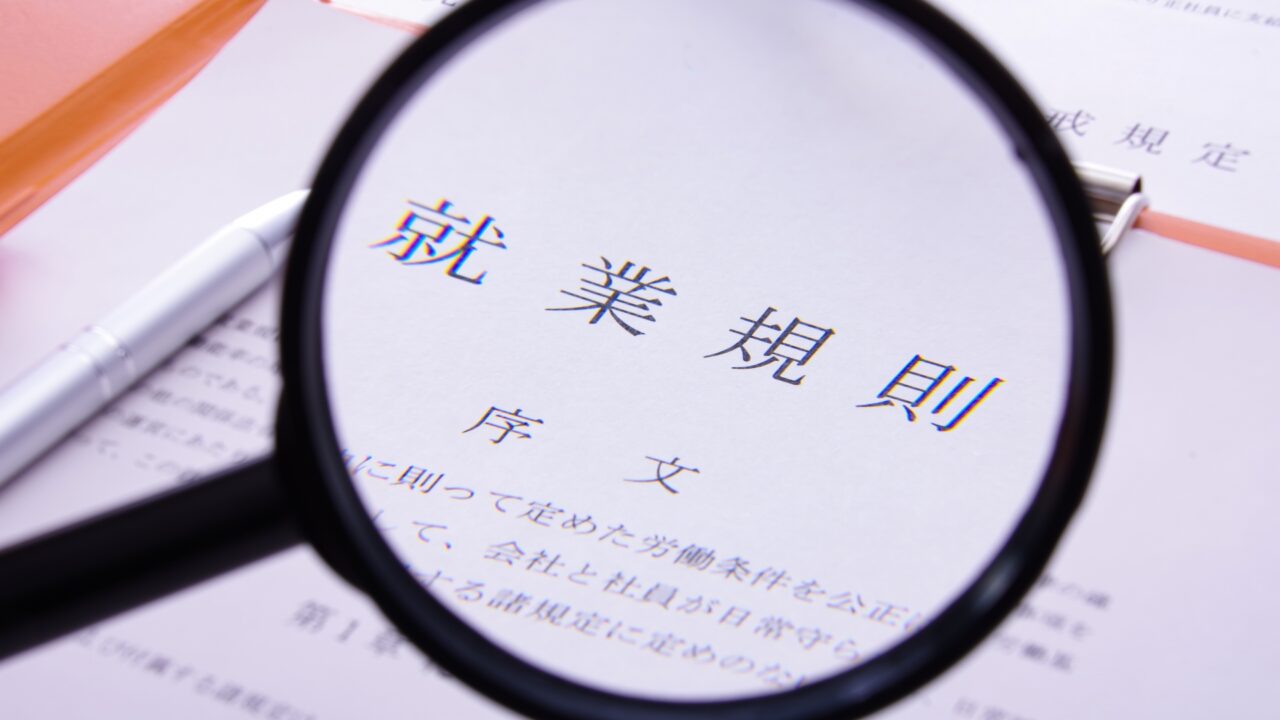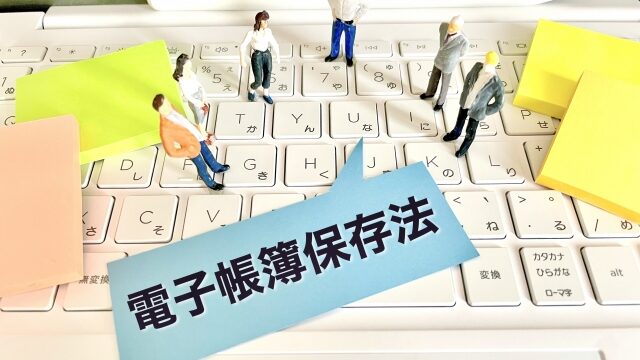従業員を雇う際、まず知っておきたいのは「労働基準法」の基本的な内容についてです。労働基準法は、日本において労働条件に関する最低ラインを定めた法律で、1947年の制定以降、改定を繰り返しながら「労働者の最低限の労働基準と権利」を保障してきました。
そこで今回は、労働基準法の基礎知識、そして実際に従業員を雇う場合に注意すべき点について解説します。
「労働基準法」とは
使用者(雇用主)と労働者の基本的な権利を守りながら、不当な労働条件から労働者を保護する法律、それが「労働基準法」です。具体的には、賃金の支払い、労働時間・休憩・休日日数、割増賃金(残業・休日出勤・深夜勤務)、解雇予告、有期労働契約の条件などが含まれており、違反すると使用者に罰則が課せられます。
労働者は、使用者に比べると弱い立場です。そのため、労働者が不当な労働条件を押し付けられないよう、国がルールを設けているのです。
労働基準法の適用範囲は原則として、「労働者」として使用者の指揮命令によって働く人すべてが含まれます。役員や幹部、監督的立場の人など、法律上は一部適用除外となるケースも存在します。また、建設業や医療業、運輸業など業種によっては、「変形労働時間制(繁閑期や時期の特性に応じて勤務時間を柔軟に変えるやり方)」の適用・例外規定が認められていることもあります。
起業・創業期の段階で注意すべきなのは、「法律で定められた最低水準より下の契約を労働者と結んでしまっていないか」という点。創業したばかりの場合は、親や兄弟、友人などに仕事を頼むケースも少なくありませんが、口約束や曖昧な契約内容になってしまうことも散見されます。
では、後にトラブルの種になるので、賃金・労働時間・休憩・休日などの条件を明示して雇用契約書や就業規則を整えましょう。
労働時間・休憩・休日の規定とその守るべきルール
労働基準法では、労働時間の原則を「1日8時間、1週40時間」としています。休憩については、「勤務が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間」と定められています。なお、使用者は休憩時間中に労働者に対して業務を命じてはいけません。
休日に関しては、「毎週少なくとも1回の休日を与えること」、あるいは「4週間を通じて4日以上の休日を与える場合は、週1休日が常に守られなくても許される」という規定もあります。休日の扱いや振替休日・代休の有無・制度としてどう運用するかは、労働契約書または就業規則で明確にしておく必要があります。
これらの条件に違反した場合、労働基準監督署からの指摘・是正勧告、罰則が科される可能性があります。休憩を与えない・休日を与えないなどのケースにおいては、未払い残業代等の請求対象にもなりやすいため、労働時間・休憩・休日の規定はきちんと理解し遵守しましょう。
賃金の支払い・割増賃金・最低賃金の基準
賃金の支払いについて、労働基準法は「通貨払い」「直接払い」「全額払い」「毎月一定期日払い」を原則としています。つまり、給料を銀行振込で一定期日に全額支払うなどが求められるということです。
時間外労働・休日出勤・深夜勤務などには割増賃金が発生するので、これにも注意が必要です。通常の時間外勤務では25%以上の割増、休日出勤であれば35%以上、深夜(午後10時〜午前5時)での労働も追加の割増があります。
また、労働基準法の範囲外にはなりますが、「最低賃金」についても抑えておく必要があります。近年の物価上昇に応じて、ここ数年、最低賃金は毎年引き上げられています。最低賃金は各都道府県によって異なりますので、会社が所在する自治体の最新の最低賃金を必ず確認しましょう。
まとめ
労働基準法は、使用者(雇用主)が労働者を不当な労働条件から守るための法律です。
特に、起業・創業期においては、親しい間柄であっても口約束ではなく、雇用契約書や就業規則で労働条件を明確にしておくことが、将来のトラブルを避けるためにも非常に大切です。
労働時間については、「1日8時間、週40時間」が原則です。休憩は勤務時間に応じて最低45分から1時間与えなければなりません。また、休日は「毎週少なくとも1回」、または「4週間で4日以上」付与する必要があります。事業の形態によっては、繁忙期や閑散期に合わせて勤務時間をコントロールすることも可能ですが、自社の事業がそれに該当するかどうかは事前に確認しておきましょう。
賃金の支払いについては、「直接」「全額」「毎月一定期日に」支払うのが基本です。さらに、時間外労働や休日出勤、深夜労働には割増賃金も発生します。また、近年は毎年のように最低賃金が引き上げられていますので、こちらも遵守する必要があります。
労働基準法を正しく理解することは、健全な事業経営の第一歩です。まずは基本的な知識からおさらいしておきましょう。
特に専門性が高い、節税対策や資金調達については、適宜アドバイスを受けながら進めていくことで、安定的な経営につながると思います。
執筆者紹介

- 税理士眞﨑正剛事務所 社会保険労務士法人眞﨑正剛事務所
- 東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。
慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」
最新の投稿
 会社設立コラム2026年1月25日外国人雇用で必要な手続きや注意点
会社設立コラム2026年1月25日外国人雇用で必要な手続きや注意点 会社設立コラム2026年1月21日創業時から備える、LGBTQへの配慮 最低限押さえるべきポイント
会社設立コラム2026年1月21日創業時から備える、LGBTQへの配慮 最低限押さえるべきポイント 会社設立コラム2025年12月25日時短勤務の従業員 給与計算の方法は?
会社設立コラム2025年12月25日時短勤務の従業員 給与計算の方法は? 会社設立コラム2025年12月21日創業直後でも整備しておきたい、ハラスメント対策
会社設立コラム2025年12月21日創業直後でも整備しておきたい、ハラスメント対策