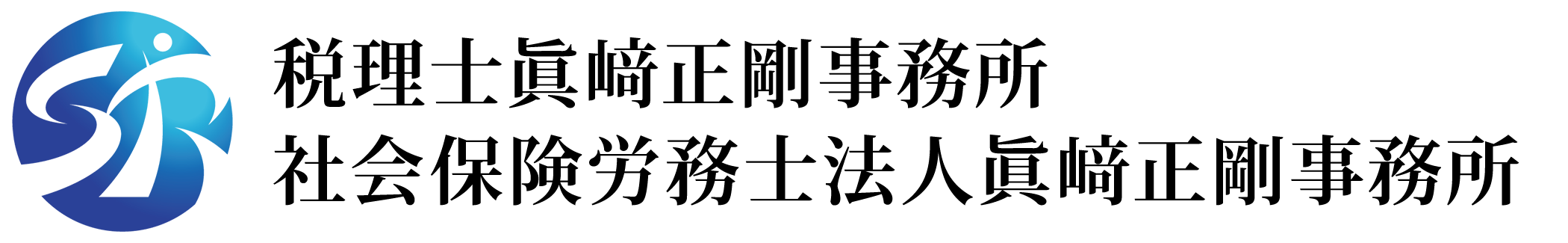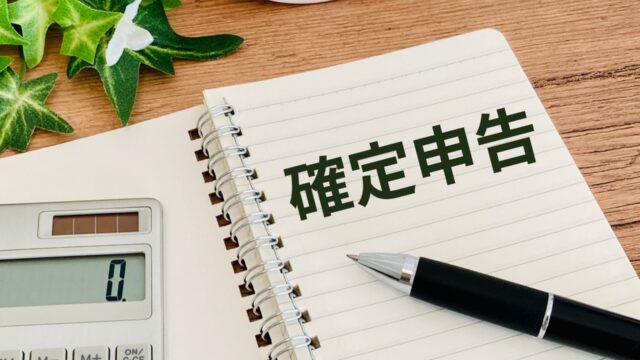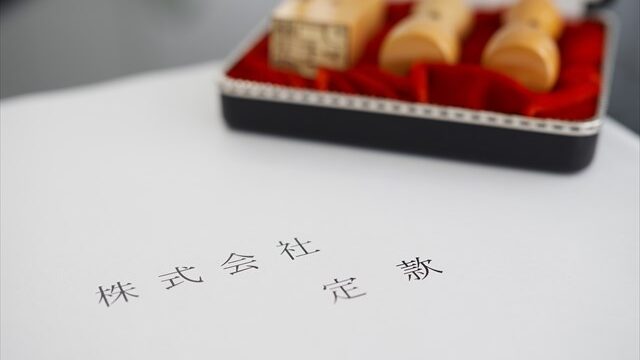従業員が気持ちよく働けるよう職場環境を整えることは、単に従業員満足度を高めるだけではなく、生産性の向上や離職率の低下、ひいては企業ブランドの向上にもつながる、非常に重要なものです。特に近年は、従業員のメンタルヘルスやワークライフバランスが注目されており、労務管理の専門家である社会保険労務士(社労士)にも、職場環境改善の相談が以前よりも増えてきました。
社労士という仕事は、労働法令に基づいた制度設計や、就業規則の整備、ハラスメント防止策の提案などを通じて、企業の健全な職場環境づくりをサポートする役割を担っています。
そこで今回は、社労士を活用することで行える「職場環境の改善」への具体策を5つの観点から解説していきます。
1. 定期的な就業規則の見直し
「就業規則」は、企業と従業員のルールブックと言える存在です。勤務時間や労働条件、勤務体制、懲戒事由などを明文化しているものですが、一部の企業においては、その内容が曖昧であるためにトラブルを引き起こす原因ともなっています。法令に適合していない、あるいは時代に即していない就業規則を使い続けている企業も少なくありません。
就業規則は時代に合わせて変化させていく必要があります。特にテレワーク制度、時差出勤、副業解禁など、働き方改革が進む中で、就業規則の内容も柔軟に対応させていく必要があります。そこで、社労士と協力し、年に1回程度は見直すことがおすすめです。
また、作成した規則を従業員に周知できていないケースも多く見られます。せっかく整備しても、従業員に理解されなければ意味がありません。社内研修やイントラネットを通じて規則の周知を図ることが重要です。
2. ハラスメント対策と相談体制の強化
ハラスメントは、職場環境を一瞬で崩壊させてしまう重大なリスクです。特にパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントは、被害者のメンタルヘルスに大きな悪影響を与えるだけでなく、その対応によっては企業の社会的信用を大きく失墜させます。
そのため事前対策として、職場におけるハラスメントの定義や行動指針を、明確に文書化しておくことを推奨します。その際、専門家である社労士と相談しながら進めていくことがポイントです。相談窓口の設置や第三者相談員の導入、外部通報窓口(ホットライン)の整備など、ハラスメント対策における多様な手段を社労士が教えてくれます。
また、管理職向けにハラスメント防止研修を実施することも効果的です。日常の言動が無意識に部下を傷つけてしまうリスクを自覚することが、ハラスメント防止への第一歩となるでしょう。
3. メンタルヘルス対策と職場の心理的安全性
従業員のメンタルヘルスを維持することは、今や企業の責任領域として認識されてきました。長時間労働や過剰な責任を負わせる仕事の削減はもちろん、人間関係のストレスからも従業員を守っていく必要があります。
メンタルヘルスへの対応としては、「ストレスチェック制度の適切な運用」が、その第一歩となります。現在、50人以上の事業所では年1回のストレスチェックが義務付けられていますが、それを単なる形式にせず、結果を活用した職場改善に活かすべきです。その際、このメンタルヘルスの結果を社労士や産業医に相談すると、いくつかの改善策を提示してくれます。なお、現在50人以上の事業所に義務化されているストレスチェックですが、3年後には「すべての事業所」に義務化の対象が拡大される予定です。
また、メンタルヘルスに関連するテーマとして、上司や同僚に対して安心して発言できる「心理的安全性」のある職場文化を醸成することも求められてきています。心理的安全性とは、ミスや意見が否定されない職場の雰囲気を指し、社員の創造性やエンゲージメント向上に直結します。
心理的安全性を高めるためには、個人の尊厳を守る意識や、コミュニケーションの基本的な姿勢などを従業員に浸透させる必要があります。また、正当な評価制度も重要になりますので、心理的安全性を改善したいという場合も、社労士に相談してみるといいでしょう。
4. 柔軟な働き方とワークライフバランスの支援
育児や介護、病気治療などによる多様な働き方への対応も、良好な職場環境には不可欠です。ご存知の通り、今までのような画一的な働き方では、社会ひいては企業を維持するには限界があります。
こうした悩みに対しても社労士からのアドバイスは有効です。フレックスタイム制や短時間正社員制度、テレワークなどの制度導入などを、積極的に提案してくれるでしょう。多様な働き方ができるようになれば社員定着率も高まるので、結果として生産性の高い組織にすることができます。
また、休暇制度の活用促進や有給取得の管理も重要です。年次有給休暇の「5日取得義務化」(2019年改正)をきっかけに、制度の見直しを行った企業も多いかと思いますが、社員がきちんと有給を取得できているかどうかをチェックし、取得できていない場合は、その後の対応など社労士から助言をもらいましょう。
5. 人事評価制度の透明性と納得感
従業員の「心理的安全性」にも通じますが、適切な人事評価は、良好な職場環境において非常に重要な意味を持ちます。曖昧な評価制度や不公平な昇進・昇給は、不満やモチベーションの低下を招き、直接的に離職につながる原因になるからです。
社労士に対して、評価制度について相談することももちろん可能です。評価基準やプロセスを明文化すること、業務内容とその責任量に合った報酬体系にすることなど、様々な視点からアドバイスしてくれるでしょう。
100%すべての人が納得のいく評価制度というものは存在しません。ただ、明らかに不公平な部分を取り除き、公正で納得感のある評価制度を目指すことこそが、良好な職場環境の要と言えるでしょう。人事評価制度の公平さは、職場の帰属意識にも大いに影響しますので、腰を据えて取り組むことをおすすめします。
まとめ
今回は、良好な職場環境を整備するのに重要な項目を5つご紹介しました。
職場環境を整備させることは、従業員の働きやすさを高めるだけでなく、企業全体の生産性や組織の安定性を維持することにもつながります。社労士の視点から見ると、就業規則の整備、ハラスメント対策、メンタルヘルス支援、柔軟な働き方の導入、公正な人事評価制度など、どれもが欠かせない取り組みです。
いずれの施策も単独で完結するものではなく、企業文化や経営方針に沿った形で運用することが大切ですが、社労士はそのプロセスを専門的にサポートする役割を担っています。法律に則った制度の策定や、いざという時の適切な対応方法など、困った時にはぜひ社労士に一度相談してみましょう。
特に専門性が高い、節税対策や資金調達については、適宜アドバイスを受けながら進めていくことで、安定的な経営につながると思います。
執筆者紹介

- 税理士眞﨑正剛事務所 社会保険労務士法人眞﨑正剛事務所
- 東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。
慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」
最新の投稿
 会社設立コラム2026年1月25日外国人雇用で必要な手続きや注意点
会社設立コラム2026年1月25日外国人雇用で必要な手続きや注意点 会社設立コラム2026年1月21日創業時から備える、LGBTQへの配慮 最低限押さえるべきポイント
会社設立コラム2026年1月21日創業時から備える、LGBTQへの配慮 最低限押さえるべきポイント 会社設立コラム2025年12月25日時短勤務の従業員 給与計算の方法は?
会社設立コラム2025年12月25日時短勤務の従業員 給与計算の方法は? 会社設立コラム2025年12月21日創業直後でも整備しておきたい、ハラスメント対策
会社設立コラム2025年12月21日創業直後でも整備しておきたい、ハラスメント対策