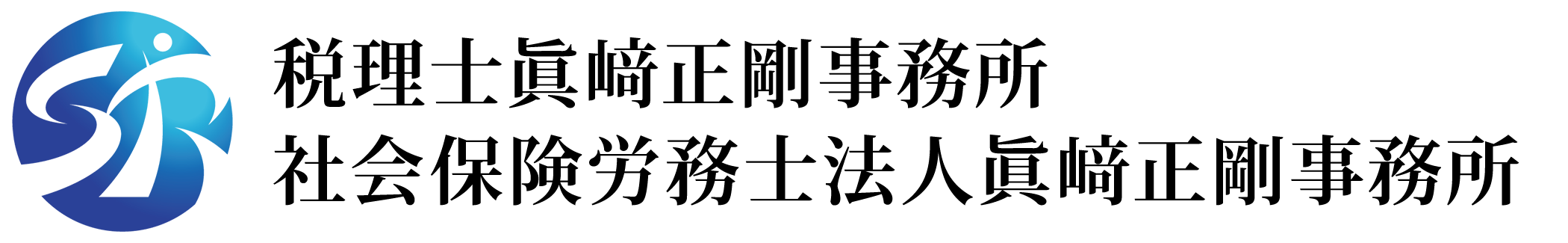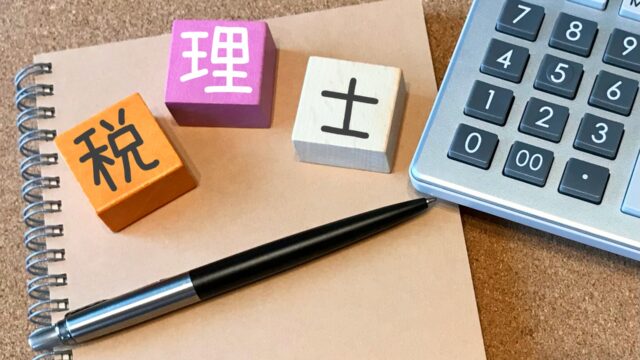近年、副業を認める企業が増える中で、副業をしている人材に仕事を依頼するケースも増えてきました。柔軟な働き方が広がる一方、企業側には労務管理や税務対応における注意点が存在します。特に、雇用契約、労働時間管理、社会保険の加入要否、源泉徴収の義務など、見落とすとリスクとなる点も少なくありません。
そこで本記事では、副業をする社員を雇う際に知っておくべき労務・税務上のポイントを解説していきます。
副業社員の雇用契約と就業規則の整備
副業として従業員を受け入れる際、まず確認すべきは「副業が法的に問題ないか」という点です。現在、日本では副業そのものは法律で禁止されていませんが、本業の企業が就業規則で副業を禁止している場合も多くあります。
そのため、最初のステップとして、副業者に仕事を依頼する前に、相手の本業先の就業規則で副業が許可されているかどうかを確認することが必要です。企業としては、就業規則に「副業者の受け入れについての方針」や「勤務時間や労働条件の調整方法」などを明示しておくことがリスク回避につながります。
また、副業先での労働が原因で本業に支障が出た場合、損害賠償責任が発生する可能性もあるため、企業間でのトラブルにも注意が必要です。
労働時間と時間外労働の管理の難しさ
本業を別に持っている人材に業務を依頼する際、特に重要となるのが「労働時間の通算」です。労働基準法第38条では、複数の事業場で働く場合、原則としてすべての勤務時間を合算して労働時間を計算する必要があると定められています。
たとえば、主たる勤務先で1日8時間働いた人が、副業先でも4時間勤務すれば、合計で12時間労働となり、超過した4時間には残業代(割増賃金)が必要になります。副業先でも、法定労働時間を超えた分に対して適切な賃金を支払わないと、労働基準法違反となるリスクがあります。
実務上、他社の勤務時間の詳細を把握するのは難しいため、本人からの申告をベースに契約時間を調整するなど、就業前に話し合いを行うことが求められます。
社会保険・雇用保険の加入条件と注意点
副業として社員を雇う場合、社会保険や雇用保険の加入要件を満たすかどうかも重要な確認ポイントです。社会保険(健康保険・厚生年金)は、1つの勤務先で週20時間以上働く、かつ月額賃金が88,000円以上など、一定の条件を満たすと加入義務が発生します。
本業先で既に社会保険に加入している場合でも、副業先での労働条件によっては、新たに加入対象となるケースがあります。また、雇用保険も同様に、週20時間以上の労働があれば副業先でも加入が必要になる可能性があります。
副業先で保険加入が必要なのに未加入だった場合、さかのぼって保険料の支払いを求められることもあるため、採用前の条件確認は怠らないようにしましょう。
税務リスク:源泉徴収と年末調整のポイント
税務面での最大の論点は、源泉徴収と年末調整の取扱いです。副業者が複数の勤務先で収入を得ている場合、年末調整を受けられるのは「主たる給与を支払う1カ所」のみと定められています。そのため、副業先では年末調整は行わず、給与支払報告書を発行する必要があります。
また、副業先での所得が一定以上(通常は20万円超)ある場合は、翌年の確定申告が必要になるため、雇用時にその旨を伝えておくことも大切です。加えて、税務署から副業先の報酬支払実態を把握されるリスクもあり、適切な帳簿管理や申告が求められます。
企業としては、「副業者=確定申告が必要な立場」であるということを本人にしっかりと説明し、源泉徴収の手続きを正確に行うことがリスク管理になります。
まとめ
副業をしている人材を採用することは、企業にとって新しいスキルや人材との出会いに繋がるチャンスです。しかしその反面、労務管理や税務対応においては、従来の社員と異なる取り扱いが必要になるため、慎重な対応が求められます。
本記事で紹介したように、就業規則の整備、労働時間の把握、社会保険の取り扱い、税務申告の対応など、すべてが企業リスクに直結します。リスクを最小限にするためには、採用前のヒアリングと、社労士・税理士といった専門家との連携が不可欠になるでしょう。
副業人材の活用を検討している経営者の皆様は、まずは自社の制度と運用体制を見直し、必要であれば専門家に相談しておくことを強くおすすめします。特に専門性が高い、節税対策や資金調達については、適宜アドバイスを受けながら進めていくことで、安定的な経営につながると思います。
執筆者紹介

- 税理士眞﨑正剛事務所 社会保険労務士法人眞﨑正剛事務所
- 東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。
慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」
最新の投稿
 会社設立コラム2026年1月25日外国人雇用で必要な手続きや注意点
会社設立コラム2026年1月25日外国人雇用で必要な手続きや注意点 会社設立コラム2026年1月21日創業時から備える、LGBTQへの配慮 最低限押さえるべきポイント
会社設立コラム2026年1月21日創業時から備える、LGBTQへの配慮 最低限押さえるべきポイント 会社設立コラム2025年12月25日時短勤務の従業員 給与計算の方法は?
会社設立コラム2025年12月25日時短勤務の従業員 給与計算の方法は? 会社設立コラム2025年12月21日創業直後でも整備しておきたい、ハラスメント対策
会社設立コラム2025年12月21日創業直後でも整備しておきたい、ハラスメント対策