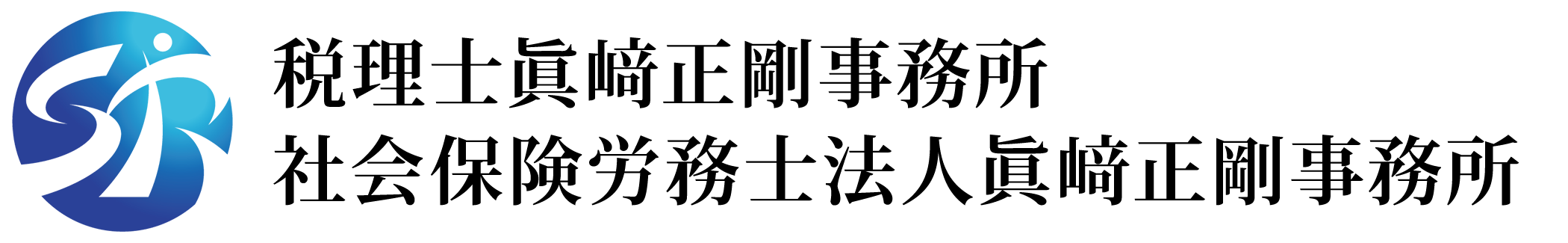「出張費や宿泊費で節税できる」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは実際、一般的によく用いられている節税方法で、多くの経営者が取り入れています。
出張費や宿泊費を経費計上するためには、まずは社内に出張旅費規定を作る必要がありますが、どのような内容にすれば良いのでしょうか。また、実際の経費計上業務で注意するべき点について、解説していきます。
出張旅費規定とは
出張旅費規定とは、出張費の精算を行う際に基準となる、社内的な規定です。出張には、実際にかかった交通費や宿泊費を実費精算する必要があるほか、出張手当ての支払いなどもあります。これら諸々の精算手続きについて、社内での基準を定めたのが「出張旅費規定」です。
なぜ、出張旅費規定があると節税になるのか?
出張をするのにかかった経費を「出張旅費」といいます。出張旅費は、所得税法上、非課税となっていて、消費税法上は仕入れ税額控除の対象となります。
具体的にどういうことか説明しましょう。例えば、遠方に出張した従業員に「出張旅費規定」に従って、出張の日当を1万円支払ったとします。
会社側はこの支払った1万円を「出張旅費」として経費扱いにできますし、仕入れ対象として所得税控除の対象にすることができます。従業員側も、この1万円は全て非課税のものとして受け取れるので、住民税や所得税の対象外です。
もし、この1万円を「営業手当」として支払った場合は、会社側としては仕入れ控除の対象にならないので消費税額を減らすことはできません。また、手当で得た収入には住民税と所得税がかかりますので、従業員側の手取りも減ってしまいます。
参照:国税庁「No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い」
「出張旅費規定」の作成に必要な項目
出張手当の支給をするためには、出張旅費規定を作成する必要があります。
出張旅費規定では、出張にかかる諸経費の取扱いを決めた条項を記載しますが、特に法律で定められているものはないので、常識の範囲内であれば、自社で自由に設定することができます。
規定に記載するのは、次のような項目です。特に決まったフォーマットがあるわけではないので、Wordなどで明文化しておくだけでも問題ありません。
出張旅費規定は、従業員だけでなく経営者にも適用されるので、1人社長の企業も作っておくことがおすすめです。
【出張旅費規定に入れる項目】
・「出張」の定義
・支給する手当て(日当、宿泊費等)の金額と条件
・支給方法(実費精算 or 定額支給)
・領収書の取り扱い
・精算の期限
・出張中の勤務時間の扱い
・出張旅費の内訳
・出張旅費の金額
・精算方法
・緊急時の対応
この中でも、特に重要な項目について詳しく解説していきます。
出張の定義
「片道100km以上を上回る場合」「他県にまたがった場合」など、出張の定義を決めます。これを満たしていない場合は、出張ではなく外出として扱われます。
出張旅費の内訳
宿泊費や交通費はもちろん、出張旅費として経費計上することができますが、一部の企業では出張中の食費や通信費も含まれていることがあります。
出張旅費の金額
相場に基づいて出張旅費の金額を定めます。宿泊費や、出張日当などのことですが、役職によって金額を変えるのも一般的です。相場については、次の章でも詳しく説明していきます。
精算方法
出張で使った経費は、基本的に領収書を提出して精算します。領収書の提出方法や期限についても定めておきましょう。
緊急時の対応について
出張時に発生した自然災害や、急な予定変更にどのように対応するかを定めます。特に海外出張ではリスクが大きいので、保険の加入を義務付けている企業もあります。
宿泊費の相場
宿泊費も、当然ながら出張経費の一部として処理できます。とはいえ、一般的な相場とあまりにもかけ離れた金額は、税務調査で指摘されてしまいます。
宿泊費の相場は役職によって異なりますが、一般従業員であれば一泊1万円以内、部長クラスであれば一泊1万円程度、役員クラスであれば一泊1万5000円程度ほどになるでしょう。海外出張であれば、相場はこれより若干引き上がります。
ただし、最近は宿泊費が高騰していることから、この相場も若干引き上がっていると考えていいと思います。
出張日当の相場
「出張日当」も、節税効果が非常に高いものです。これも出張旅費規定に明記しておく必要があるので、一般的な相場を理解しておきましょう。
役職によって支給額は異なり、一般社員であれば1日あたり2000円ほど。部長クラスであれば3000円程度になるでしょう。日帰りなのか宿泊なのか、また国内なのか海外なのかによっても金額を別途設定することができます。
まとめ
出張費や宿泊費は、経費として認められる業務費用です。
しかし、出張旅費規定が無いと、適切な経費として扱うことができないケースもありますので、まだ作っていないという経営者は、すぐにでも作成することをお勧めします。
税務調査においても、「その出張経費は正しいものなのか?」という視点でチェックされます。これらの経理計上が、出張旅費規定に則ったものであること、またその規定が常識的な内容であることが問われます。
正しく節税するためにも、出張費・宿泊費を理解し、適切な出張旅費規定を作成しましょう。特に専門性が高い、節税対策や資金調達については、適宜アドバイスを受けながら進めていくことで、安定的な経営につながります。
執筆者紹介

- 税理士眞﨑正剛事務所 社会保険労務士法人眞﨑正剛事務所
- 東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。
慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」
最新の投稿
 会社設立コラム2026年1月25日外国人雇用で必要な手続きや注意点
会社設立コラム2026年1月25日外国人雇用で必要な手続きや注意点 会社設立コラム2026年1月21日創業時から備える、LGBTQへの配慮 最低限押さえるべきポイント
会社設立コラム2026年1月21日創業時から備える、LGBTQへの配慮 最低限押さえるべきポイント 会社設立コラム2025年12月25日時短勤務の従業員 給与計算の方法は?
会社設立コラム2025年12月25日時短勤務の従業員 給与計算の方法は? 会社設立コラム2025年12月21日創業直後でも整備しておきたい、ハラスメント対策
会社設立コラム2025年12月21日創業直後でも整備しておきたい、ハラスメント対策